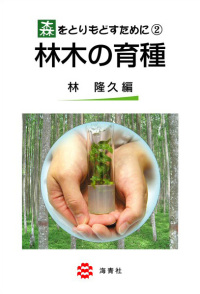|
|

|
|
森をとりもどすために2 林木の育種
交配による育種法から遺伝子組換え法までの林木育種技術を紹介。遺伝子組換えを不安な技術であると考える人が多いが、交配による育種の延長線上にその技術はある。「地球救済のための樹木育種」への道を探る。
はじめに
1章 林木育種の過去・現在・未来 (近藤禎二/森林総合研究所林木育種センター)
1.品種を気にしないで山に木が植えられている
2.林木育種の過去
3.林木育種の現在
4.林木育種の未来――バイオテクノロジーが林木育種を変える――
2章 地球温暖化を防ぐために (藤澤義武/森林総合研究所林木育種センター)
1.地球の温暖化と炭素の貯蔵庫としての樹木
2.木材の利用は地球を守る
3.林木育種で森の能力向上
4.炭素固定能力を高める育種
3章 花粉を飛ばさないスギを求めて (福田陽子/森林総合研究所林木育種センター)
1.スギ花粉の特徴
2.花粉の少ないスギ品種の育成
3.雄性不稔スギの発見
4.スギと人間の復縁に向けて
4章 キシログルカンと組換えポプラ (林 隆久/東京農業大学)
1.細胞壁が植物の成長をコントロールしている
2.キシログルカンに魅せられて
3.細胞壁をゆるめる遺伝子
4.組換えポプラの誕生
5.組換え樹木の海外展開
6.虚学と実学
5章 樹木の成長と形態調節 (馬場啓一/京都大学生存圏研究所)
1.木材とは何か
2.樹木の成長と姿勢制御
3.ヘミセルロースの役割と分子育種
6章 リグニン改変のバイオテクノロジー (堤 祐司/九州大学大学院農学研究院)
1.ポスト化石資源としての木質バイオマス
2.木質バイオマスの循環型エネルギー利用とバイオテクノロジー
3.リグニンとはどんなもの?
4.応用を支える基礎研究
5.リグニンの改変を目指したバイオテクノロジー研究
6.リグニンの遺伝子組換えに関わる解決すべき問題
7章 樹木の凍らない水 (藤川清三/北海道大学大学院農学研究院)
1.樹木は凍結抵抗性のチャンピオンである
2.樹木の中には凍らない水をもつ細胞がある
3.なぜ、木部柔細胞の水は凍らないのか?
4.過冷却する木部柔細胞に発現する遺伝子の同定
5.過冷却の増進と関連すると推定される遺伝子の機能解析の試み
6.おわりに
8章 モデル樹木としてのポプラ (西窪伸之/王子製紙株式会社森林資源研究所)
1.樹木のゲノム研究
2.モデル植物について
3.ポプラゲノムプロジェクト
4.ゲノム配列から何が分かるのか?
5.ポプラで重要な遺伝子を見つけるために
6.ポプラの遺伝子情報から分かってきたこと
7.他の樹木への応用は可能か?
9章 組換え技術の信頼性向上 (海老沼宏安/株式会社日本紙パルプ研究所)
1.組換え技術への期待
2.自然の力を活用
3.植物の組換え技術の課題
4.MAT ベクターシステムの開発
5.SDI ベクターシステムの開発
6.今後の展開
10章 環境安全性の評価と審査 (川口健太郎/農研機構作物研究所)
1.安全性を確保するための枠組み
2.生物多様性条約のカルタヘナ議定書
3.カルタヘナ法の下での遺伝子組換え生物の使用申請、 審査、承認の手順
4.遺伝子組換え生物の環境安全性を考える上での重要 な概念
5.生物多様性影響評価の方法
6.遺伝子組換え植物の情報
7.「生物多様性影響を生じさせる可能性のある性質」 を持つかどうかの判断
8.生物多様性影響の総合的評価
9.おわりに
11章 遺伝子組換え植物の安全と安心 (外内尚人/元(社)STAFF)
1.遺伝子組換え作物とは?
2.従来の品種改良法と遺伝子組換え法
3.主要な遺伝子組換え作物
4.世界の遺伝子組換え作物栽培状況
5.食卓の遺伝子組換え食品と表示制度
6.遺伝子組換え作物についての安全と安心
12章 樹木の遺伝子組換え実験(海田るみ、朴 龍叉、澤田真千子)
1.組換えポプラの作出
2.組換えファルカタの作出
3.コンタミについて
用語解説 |